「木工の街・鹿沼」のルーツは、徳川家ゆかりの日光東照宮にある。
いろは君の住む静岡と同じなので、嬉しくなった。
静岡の木工も、徳川家康の駿府城や、徳川家光の静岡浅間神社造営にルーツがある。同神社の社殿は、総漆塗り極彩色の豪壮華麗な建築で、〝東海の日光〟といわれている。造営で全国から集められた職人が定住し、指物、下駄、漆器などの工芸品が発展した。
鹿沼では、それが建具と彫刻屋台である。
「木工の街」として、建具は認識していた。実際に街に行き、木工でできた絢爛豪華な彫刻屋台を見ると、「屋台の街」の印象が強くなる。
中心市街地である観光・文化の拠点「屋台のまち中央公園」に「屋台展示館」がある。屋台の歴史、技術などがよくわかる施設だ。


入口正面の柱に、彫工・黒崎嘉門氏によって彫られた迫力のある龍や獅子が迎えている。籠彫りの玉を持つ龍の彫刻である。絵画でもよく、龍が玉を持っているのをよくみる。
その意味は、「如意宝珠」で、サンスクリット語で、「意のままに様々な願いをかなえる宝の珠」のことである。また、「子宝の玉」とも言われている。
それが、一本の木から彫っていて、籠に入った丸い大きな玉を持っている。後から玉を入れることはできない。職人技で、くり抜いて彫っていることに驚く。
館内には、江戸時代に作られた屋台が三台展示されている。今なお祭りで使われるものだ。
彩色豊かなものと白木造りで地味なものがある。文政十年(一八二七年)、神事祭礼の質素倹約が言い渡された後に作られたものだった。時代によって屋台も変わるのだ。
毎年、「今宮神社」の秋まつりで、町ごとに二十数台の屋台が曳かれる。男衆が屋台の上に立ち、勇壮である。複数の屋台がお囃子の競演をする「ぶっつけ」で、祭りは盛り上がる。

平成15年(2003年)に国の重要無形民俗文化財に指定された。平成28年(2016年)には、全国33の「山・鉾・屋台行事」の一つとして、「ユネスコ無形文化遺産」に登録された。
鹿沼市文化交流館内の「郷土資料展示室」にも、実際に使われる屋台が2台展示されていて、そちらでも熱心に説明してくれる。
“屋台愛”が熱く、人情と絆のある街を感じる。
コロナ禍で、祭りは二年連続で中止となっている。市民も屋台も、〝晴れ舞台〟を心待ちにしている。

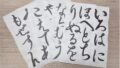

コメント