広島市の平和記念公園近くのオフィス街に、ひっそりと趣のある建物がある。
原爆の被災に耐え、今も残る旧日本銀行広島支店の隣にある「頼山陽史跡資料館」である。
「頼山陽」の名は聞いたことがあるが、何をした人だろう?
趣のある佇まいに惹かれ入った。

-646x1024.jpg)
館内では、常設展「頼山陽の生涯」と特別展「頼聿庵の書~大書の魅力~」が展示されていた。山陽は、江戸時代後期に活躍した漢学者・文人で、幕末の志士たちに大きな影響を与えた歴史書『日本外史』の著者であった。
安永9年(1780)、大阪で生まれた。翌年、父春水が儒学者として広島藩に登用され、移住した。父が藩から拝領した屋敷跡に資料館がある。


幼い頃より向学心旺盛で、19歳の時に江戸に一年間遊学し、昌平坂学問所で学んだ。
その後、結婚をするが、21歳の時、好学の志やまずに脱藩の重罪を犯す。
潜伏先の京都から連れ戻され、死罪こそ免れたが、廃嫡(家を相続させないこと)となり、藩法により妻と離縁した。
特別展の聿庵は、山陽の長男で、離縁した妻との子である。誕生後、頼家に引き取られ、祖父母の子として育てられた。
その後、山陽は自宅の離れで五年間の幽閉生活を送った。家の外に出ることも許されないなか、学問に没頭し、代表的な著作『日本外史』の草稿を書き上げた。
その居宅は、原爆により焼失したが、昭和33年(1958)に復元されて国の史跡になっている。


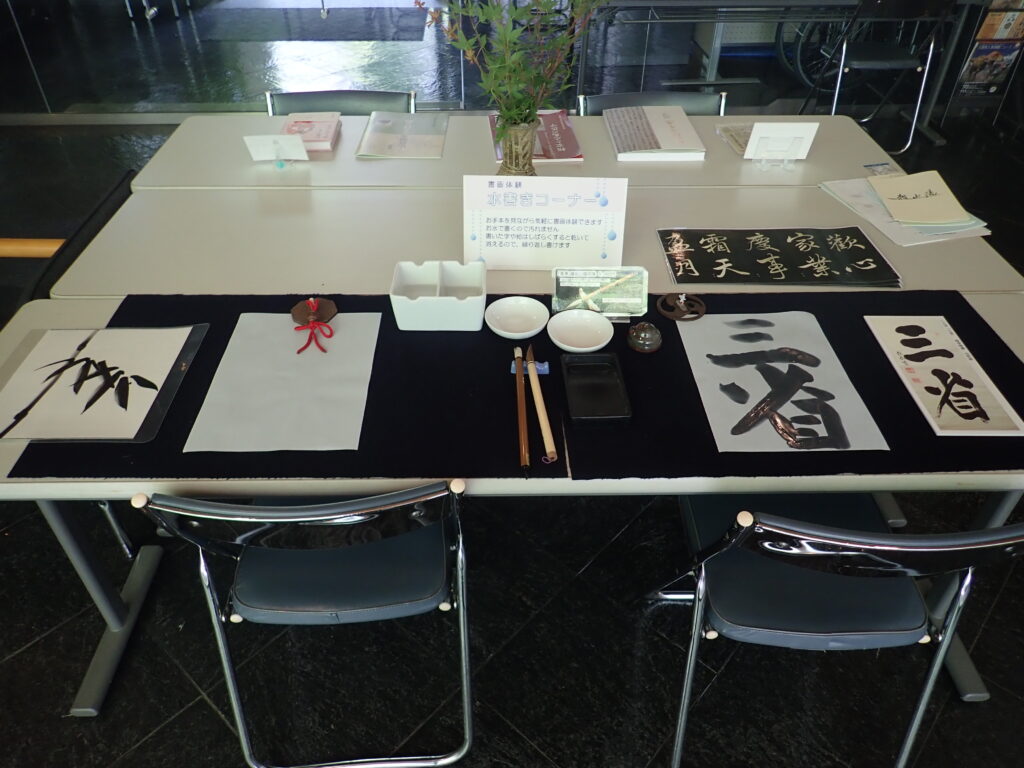
幽閉生活が解かれた後、塾の講師を務めた。しかし、三都(江戸・京都・大坂)で学び名を挙げたい志が強く、三十二歳の時、京都に出た。
京都で私塾を開きながら、文政9年(1826)に、22巻にも及ぶ『日本外史』を完成させた。翌年、松平定信に献上し、「穏当にして中道をうる」(無理がなく理屈にかなっており、偏っていない)と評価を受け、天下に認められることとなった。
『日本外史』は、源氏・平氏から徳川氏にいたるまでの武家の興亡を漢文で記した歴史書である。幕末から明治にかけて広く読まれ、幕末の志士たちに大きな影響を与えた。
書き上げた感想を詠んだ漢詩が残っている。
二十餘年成我書(二十余年我が書を成す)
書前酹酒一掀鬚(書前酒を酹いで一たび鬚を掀ぐ)
此中幾個英雄漢(此の中の幾個の英雄漢)
諒得吾無曲筆無(吾が曲筆無きを諒得するや無や)
大意は、『二十余年の歳月を費やして『日本外史』は完成した。この書を前に、酒を注いで神霊を祀り、心ゆくまで杯を傾けた。この書の中には幾多の英雄たちを描き出しているが、彼らは私の筆に曲筆(事実を曲げて書くこと)のないことをわかってくれるだろう。』である。
どれだけ情熱を注いで完成させたかが伝わってくる。
脱藩の重罪まで犯し、幾多の困難にもめげず、生涯を『日本外史』完成に捧げた山陽の人生に感動した!



コメント