新聞には書籍の広告が多くある。そのなかで以前から気になっていたのが、実業之日本社の「本多静六シリーズ」である。
代表作は「人生計画の立て方」、「私の財産告白」、「私の生活流儀」である。
‟日本の公園の父”であり、‟蓄財の神様”とも言われる実践哲学に興味を惹かれる。
その本を読む前に、出身地・埼玉県久喜市にある「本多静六記念館」を訪ねた。


同館は、久喜市菖蒲総合支所の5階にある。
役所の一室にあるが、中に入ると別世界で静六翁の業績、人と成りに浸ることができる。
静六翁は、江戸時代末期の慶応2年(1866)、折原家に生まれた。明治17年(1884)、東京山林学校(後に東京農林学校、現在の東京大学農学部)に入学、向学心が旺盛だった。
在学中に、本多晋の娘・銓子との縁談話しがきた。結婚する気はなく、「卒業後、ドイツに四年間留学させてくれるならなら結婚する」と断るつもりで答えた。
すると、惚れ込んでいた本多家が快諾し在学中に結婚、婿となり本多姓となった。
義理の父は、徳川慶喜の家臣で、彰義隊頭取を務めていた。怪我により上野戦争には参戦できず生き残った。明治に入り、慶喜とともに静岡に移ったが、同じく家臣だった渋沢栄一の勧めにより明治新政府に出仕した人物である。
卒業後、約束通りドイツに留学させてもらったが、義理の父が預けていた銀行が倒産、仕送りの送金が止まった。
しかし、奮起して通常四年間かかる過程を二年間で修了するという目標を立てた。
そして、毎晩睡眠3~4時間の猛勉強をして、ミュンヘン大学博士号を取得した。ドイツ語の勉強もあるなか達成したその努力に驚く。
帰国後、東京農林学校助教授となった。その後、日本初の林学博士となり教授となる。


34歳の時、計画されながらまとまっていなかった日比谷公園の設計案に意見を求められ答えた。すると、見込まれて設計を担当することになった。
それまで日本に公園がなかったから、誰も設計をしたことがなかったのだ。当然、静六翁も設計をしたことがない。それを引き受けて二年後に開園、東京のシンボル的な公園となった。
以降、日本全国百箇所以上の公園設計に携わった。水戸の偕楽園、明治神宮の森、奈良公園など著名な公園ばかりである。自然と調和し、景観や都市計画をも加味した公園は、市民の憩いの場とともに観光地として名所になっている。
それまで誰もやったことがない公園設計に挑み、生涯の仕事として取り組んだ結果、‟日本の公園の父”といわれるようになった。パイオニア精神で、後世に残る仕事をした静六翁の並外れた努力に感動した。


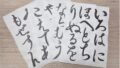
コメント